仕事、育児、家事…毎日大忙し。でも、そんな中でも“何か資格を取りたい”と思ったことはありませんか?
私は独身時代には某大手通信講座に申し込んでは三日坊主を繰り返す失敗を多数経験。
しかし、家庭を持った今は、大事なお金を無駄にすることは避けたい。なるべくお金はかけたくない。そこでこの記事では、働くママが無理なく、最小限の費用でFP3級を取得するための実践的なステップをお伝えします。
この記事を読めば必要な手順が分かります。
FP3級を勉強したい!資格を取りたい!と考えている方はぜひ最後まで読んでください。

当時は3歳の子を育児をしながらのフルタイムの状況でした。
合格までの勉強期間は人それぞれ千差万別ですが、私自身は覚えもあまり良くなかったので約3ヶ月というスケジュールを立てて進めていきました。
FP3級についての基本情報
FP3級とはどんな資格?
FP3級はいわゆるお金の基礎知識と言える資格になります。将来の教育費や住宅ローンについて計画を立てやすくなったり、ママにとって大きなメリットがあります。学ぶ内容は以下の6分野となり多岐に渡ります。暮らしとお金に関する知識が必要となります。
⚫️ライフプラン
⚫️リスク管理
⚫️金融資産運用
⚫️タックスプランニング
⚫️不動産
⚫️相続・事業承継
順番に勉強する必要はなく、6分野をどこから始めても大丈夫です。私は仕事の関係から一番自分に身近にあったタックスプランニングから勉強を行いました。
試験概要について
試験内容についてですが、学科と実技があります。学科は共通試験となります。
実技がは大きく分けて二つとなります。
(日本FP協会):資産設計提案業務の1種類
(きんざい) :個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務の2種類
受検者は自分が得意とする分野や学びたい分野に合わせて、いずれかの実技試験を選択することができます。
試験時間、出題数と形式および合格基準については以下のようになります。
(日本FP協会より出典)
| 試験時間 | 問題数 | 出題形式 | 合格基準 | |
| 学科試験 | 90分 | 60問 | 多肢選択式 | 36点以上 (60点満点) |
| 実技試験 | 60分 | 20問 | 多肢選択式 | 60点以上 (100点満点) |
受検料についてですが、学科のみ4,000円(非課税)、実技のみ4,000円(非課税)となり、学科と実技をあわせて受ける場合は、受検料が8,000円(非課税)となります。
支払い手数料が別途事務手数料が107円かかります。コンビニ決済も別途手数料がかかります。
試験日程について
3級のFP試験は2024年から一斉方式のペーパー試験から全国で随時受検ができるCBT試験に変更になっています。ちなみFP2級も2025年からCBT試験方式に変更となります。
私は旧式のペーパー方式で受検をしています。FP試験ではありませんが、簿記の試験を受ける際もCBT方式で受検しました。
紙媒体とネット試験ではかなり勝手が異なりますので、本番までにネットの試験方式に慣れておくことは必須です。
2級・3級FP技能検定 学科及び実技試験(資産設計提案業務) ※CBT試験
(日本FP協会より出典)
| 試験日 | 合格発表日 | 法令基準日 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日~4月30日 | 5月19日 | 2024年4月1日 |
| 2025年5月1日~5月24日 | 6月16日 | |
| 2025年6月1日~6月30日 | 7月15日 | 2025年4月1日 |
| 2025年7月1日~7月31日 | 8月18日 | |
| 2025年8月1日~8月31日 | 9月16日 | |
| 2025年9月1日~9月30日 | 10月16日 | |
| 2025年10月1日~10月31日 | 11月18日 | |
| 2025年11月1日~11月30日 | 12月15日 | |
| 2025年12月1日~12月28日 | 1月19日 | |
| 2026年1月6日~1月31日 | 2月17日 | |
| 2026年2月1日~2月28日 | 3月16日 |
※2級・3級CBT試験 休止期間
| 2025年度 | 2025年5月25日~5月31日 |
| 2025年12月29日~2026年1月5日 | |
| 2026年3月1日~3月 |
資格取得までのステップ
資格取得のステップとして次の4つを考えて行いました。
継続するために10分でもいいから勉強の時間に充てることを意識して進めていくことが重要です。
最初は勉強時間が全然取れず、「やっぱり無理かも」と考える日もありました。
でも、続けていくうちに少しずつ知識が増えて自信がついてきました。たとえ短時間でも毎日、受験勉強に向き合うことで、きっと習慣化されていきます。
学習スケジュールの立て方
時間の確保について
仕事に育児に家事にとにかく多忙なママさん達。
正直、時間なんてない!なんて思う方もいらっしゃると思います。
私自身もそうでした。あれもこれもやらなきゃいけない。
完璧でないといけないとどこか自分を追い詰める感覚になることもありました。
でも、ふと1日を見直してみると見つけることができる隙間時間。
例えばこんな時間はありませんか?
・朝、家族が起きてくるまでの30分
・仕事のお昼休みの30分
・子どもを寝かしつけ後の30分
などです。
上記の時間を単純計算しても1時間30分確保できるでしょう。
もちろんこれよりも短い時間でしか確保できな方もいると思います。
それでも毎日勉強する習慣化のためにもこの隙間時間の確保は有効です。
平日は忙しくて難しい方は30分くらいにして休日にまとめて時間を確保するのもよいでしょう。

私は寝かしつけではどうしても子どもと寝落ちしてしまうので、代わりに朝早く起きて勉強時間に充当していました。(朝活のメリットを参照)
SNSやYouTubeを何気なく見ていた時間も勉強に変更していたので短くても最低1時間は確保できました。
誘惑に負けないためにスマホは自分の見えない・手に取れないところに置くのもよい方法です。
学習スケジュールについて
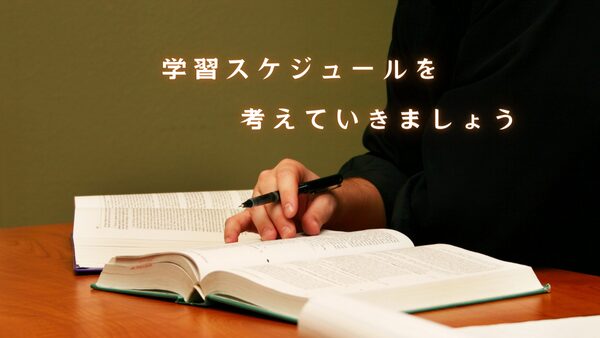
試験の本番の日から逆算して3ヶ月のスケジュールを立てました。
<1〜2週間目:インプット時期①>
テキストとYouTubeを併用して知識を身につけていく。
詰め込み式の暗記ではなく、お金の知識として身につけるためにここは時間をかけて行いました。
私が使用したテキストはLECのFP3級の速習トリセツシリーズです。
カラー刷りで文字も見やすく、図解も豊富で初めて勉強する方にもとても分かりやすい内容です。
また、YouTubeで発信されているほんださん / 東大式FPチャンネルも併用しました。
ほんださんが監修しているので内容がテキストとリンクがされており、とても便利です。
価格はそれぞれ税込み1,760円です。
ただ、ここでは分からない箇所があっても気にせず全体像を把握するために進めていきます。

また、勉強期間中の隙間時間におすすめなのが、アプリを活用した学習です。
私が使用したのは「FP3級ドットコム」というアプリでした。
このアプリはクイズ形式で問題を解くことができ、正答率の確認も可能です。
学科試験や実技試験の対策に使える上、法改正にも対応しており、とても便利です。
さらに、無料で利用できるのも嬉しいポイントです。
個人差はありますが、テキストを購入せずにYouTubeや無料アプリだけで勉強する方もいらっしゃいます。その場合、教材費がかからず、受検料のみで済むのが大きなメリットです。
<3週間目〜1ヶ月半目:インプット時期②+アウトプット時期①>
テキストを1周読み終えたら、次にもう一度テキストを確認しながら、YouTubeの解説動画を活用して2周目に進みます。
この段階では、テキストに対応した問題集も併用して解いていきます。
問題集は正誤を確認できる仕様になっているため、自分がどこを間違えたのかが一目で分かります。
2周目では、1周目よりも理解度が高まっているはずでしょう。
間違えた箇所は、その都度テキストに戻って確認し、繰り返し復習していきます。
テキストを読んで重要なところや分からないところがあればノートに書き出していました。
<1ヶ月半目〜2ヶ月半目:アウトプット時期②>
試験勉強も後半となり、アウトプットに重点を置いていきます。問題集を2周目を行いましょう。
もし、時間が取れる方はさらに問題集を3周目をチャレンジしてみてください。
ここまでくると知識もかなり身につき、問題を解くスピードもアップしているはずです。
注意事項は問題集は3周以上は解かなくてよいと思います。
理由は回答を覚えてしまっている可能性があるためです。
ある程度の問題を解いたら次にステップアップしましょう!
<2ヶ月半目〜3ヶ月目:試験準備時期>
知識も理解も深めたところで、本番に向けた勉強を進めていきましょう。
試験問題集を購入しなくても紹介したLECの書籍の中で「CBT試験プログラム体験模試」を搭載しいます。ネット試験であるCBT方式にも慣れておく必要がありますのでオススメです。
また、日本FP協会のHPでは過去の試験問題が掲載されています。
印刷やダウンロードをおこない、繰り返し解いていき自分の実力を把握をしてください。
間違えた箇所は解説やテキストを確認し、知識を確実なものにしていきましょう。
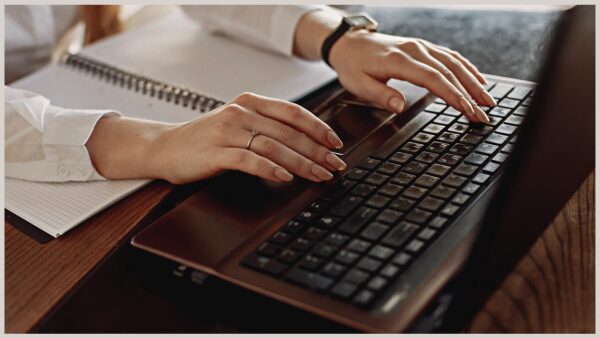
<試験当日>
いよいよ試験本番当日となります。
私が必要と思う持ち物リストをあげさせていただきました。
当日の持ち物についてはCBT方式に変更になってからは受検票は無くなり、本人確認書類が必要となります。
試験自体は、学科も実技も空席があれば同日で受検できますし、日にちを別日に設けても受検できます。
(持ち物リスト)
・本人確認書類
・使っていた参考書等
・カイロ(冬場は必須)
・手袋(冬場は必須)
・ハンディファン(夏場は必須)
・昼食(もし、時間を空けて受検するならば必要)
会場の選択は自分で行えますが、居住地から会場までは近い場所であっても初めて向かう場所の方もいらっしゃると思います。
公共交通機関でいく場合も自家用車で行く場合も土地勘がない場所の場合はきちんと受検場所の確認、時刻表や目的地までのルート確認等を事前に行なっておきましょう。
受検する時期は真夏や真冬のときもあると思います。暑さ・寒さ対策についてもきちんと準備をしておきましょう。
一生懸命に勉強してきたのに試験当日に体調を崩しては本末転倒です。
試験会場にはスマートフォンや腕時計、筆記用具や電卓参考書は自席には持ち込めず、会場のテストセンターに設置された鍵付きのロッカー等に保管することになります。
メモ用紙や筆記用具はテストセンターで貸し出されますので、それを使用します。
緊張すると思いますが、今まで頑張ってきた自分自身を信じて試験に臨んでください。
まとめ
今回は、働くママさんたちに向けて、FP3級取得までの実践ガイドをお届けしました。
私が紹介したスケジュールは、余裕を持たせたものになっていますが、勉強の進め方は人それぞれです。短期間で取得できる方もいれば、時間がかかると感じる方もいらっしゃると思います。
FP3級の勉強は決して簡単ではありませんが、一歩ずつコツコツと進めていけば、必ずゴールにたどり着けます。
私はFPの勉強がとても楽しく、2級まで取得することができました。
その内容については、また後日ご紹介させていただきます。
まずは、1冊の参考書を手に取ってみることから始めてみませんか?
どんな小さな一歩も、きっと未来につながります。心から応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
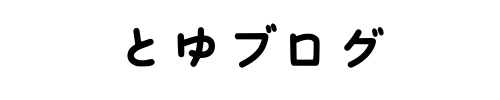
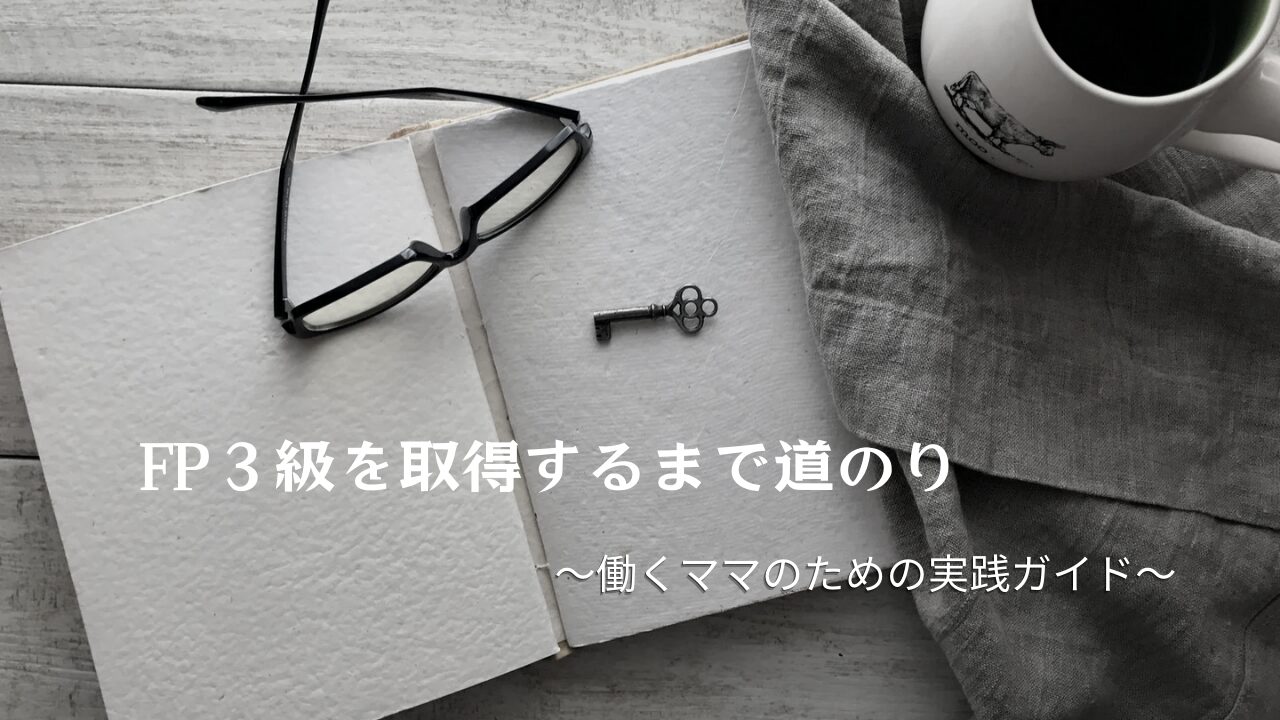


コメント